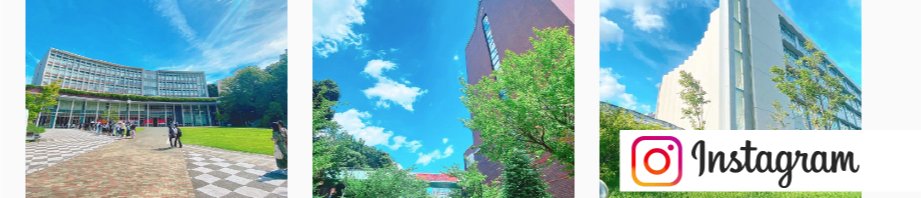子どもが子どもらしくいられる社会とは?
112限目 子どもと失敗
『子どもには失敗する権利がある?』
人間科学部 現代子ども教育学科
子どもには失敗する権利がある。

ポーランドの小児科医として、教育者として、その生涯を子どもたちのために捧げたヤヌシュ・コルチャック(1878〜1942年)は、自身が掲げた「子どもの基本的人権」のひとつに「失敗する権利」を挙げています。
そこには、子どもは失敗を通じて学び、成長していく存在であること。
そして、子どもが失敗を恐れずいきいきと活動し、それを見守る環境を作ることが周囲にいる大人の役割である、というメッセージが込められています。
大切なことは、子どもが失敗して傷ついたり、悲しんだり、不安な気持ちを抱えているときは、周りの大人たちは子どもの気持ちに寄り添い、受けとめてあげること。
失敗したっていいんだよ。ここまでよくがんばったね。
大人たちからそんなメッセージを受けとった子どもは、その時は失敗したとしても、挑戦したこと自体が大切だと思えるようになり、もう一度チャレンジしようという気持ちがわいてきます。
しかし、今の日本の子どもたちは、失敗を過度に恐れたり、失敗の経験が少ない傾向にあると言われています。
その背景には何があるのでしょうか。
失敗は、次のステップに進むための重要なプロセス。

「あの子はできるのに、うちの子はなんでできないの」と、わが子を他の子と比較して、子どもを頭ごなしに叱りつけたり、失望したり。
あるいは、子どもが失敗をしないように先回りして声をかけたり、代わりにやってあげてしまったり。
それはわが子への愛情ゆえの言動や行動かもしれませんが、結果的に失敗する権利を奪うことになり、主体的に行動する力や困難を乗り越える力、挑戦する勇気など、失敗の経験から育まれる力が十分に育たないことになってしまいます。
でも、子どもの失敗体験は大切なこととわかっていても、子育ては理想通りにいかない、「見守る」と「手助け」のさじ加減が難しい、と悩む方も多いかもしれません。
そんなときは、子育てや子どもとの関わり方を「権利」の視点から考えてみるのも、ひとつの方法。
「子ども」という存在をあらためて見直し、子どもの立場や目線に立った接し方に変わるきっかけとなるかもしれません。
196の国と地域が締結する「子どもの権利条約」とは?

子どもの権利条約は、世界中すべての子どもが持つ基本的人権を定めた条約で、1989年に国連総会で採択され、日本は1994年に批准しました。
この権利条約を活動基盤とするユニセフは、締約国が条約を実現していくための原則として、①差別の禁止、②子どもの最善の利益、③生命、生存及び発達に対する権利、④子どもの意見の尊重の4つを定めています。
この4つの原則は、2023年4月にスタートした「こども基本法」の基本理念として盛り込まれ、日本に住むすべての子どもの権利が保障され、子どもの意見が聴かれ、その声を社会のしくみに生かしていく第一歩になると期待されています。
ちなみに、冒頭でふれたコルチャックの「失敗する権利」はこの子どもの権利条約には入っていませんが、彼の遺した言葉や権利大憲章は、後にポーランド政府を介して子どもの権利条約に結実。コルチャックの子どもへのまなざしは、権利条約の精神となって、いまも世界に伝え続けています。
子どもの権利を周りの大人が知ることの大切さ。

子どもの権利条約が日本で批准されて30年が経過しましたが、児童虐待やいじめ、不登校などが深刻さを増しており、すべての子どもたちの権利が守られているとは言いがたい状況があります。
子どもは生まれながらにして心身ともに健やかに生きる権利があり、大人や国にはその権利を守る義務と責任があります。
子どもが子ども期を子どもらしく過ごし、その可能性や能力を十分に伸ばすことのできる社会を育むために、私たち大人がすべきことは、まず、子どもの権利を学び、理解すること。
子どもの権利を知り、学び、子どもの権利が子どもにも大人にも大切であることに気づき、毎日の生活のなかで実践できる大人が増えていくことが、子どもの権利が守られ、尊重される社会をつくっていくことにつながっていきます。
子どもの生きる環境を見つめ、健やかな成長を助ける
それが人間科学部 現代子ども教育学科
・・・
参考
ユニセフ|「子どもの権利条約」
こども家庭庁|「こども基本法」
2018年7月掲載 『車内の金城学院大学112限目』 はこちら
金城学院大学 人間科学部 現代子ども教育学科のページはこちら
・・・